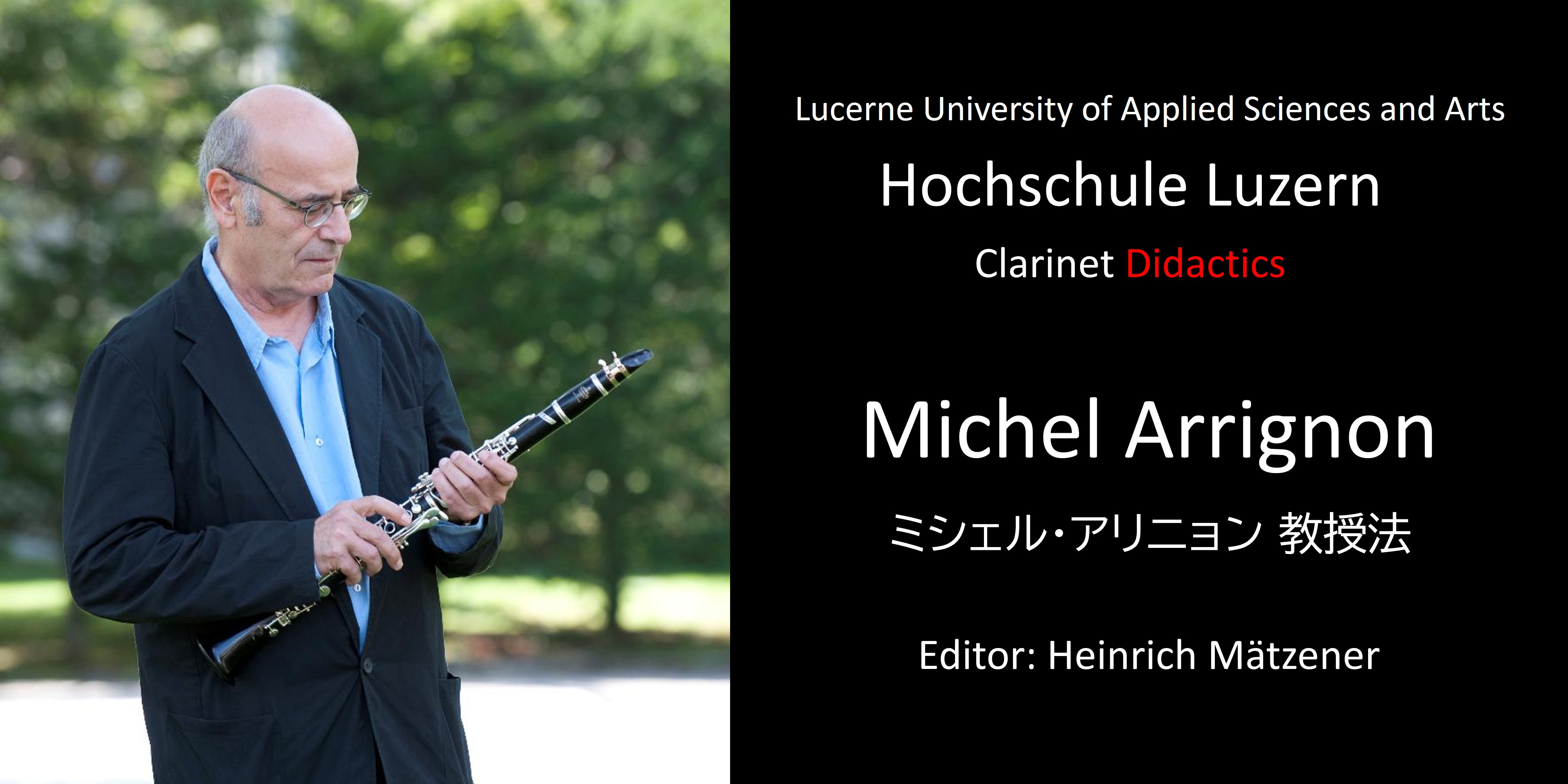
ミシェル・アリニョン氏 教授法 — クラリネット教育における哲学と実践(目次)
フランスを代表するクラリネットの巨匠、ミシェル・アリニョン氏。氏は演奏・教育・楽器開発の三領域にわたり半世紀にわたって基準を築き、その音色と方法論は今日も世界の教育現場の規範となっています。
本シリーズでは、彼がハインリッヒ・メッツェナー教授(ルツェルン応用科学芸術大学)に2018年に語った教育哲学と奏法理論を、全13章にわたって完全翻訳の形で紹介します。
翻訳公開許可:Heinrich Mätzener氏 および Camille Arrignon氏 / © Haute École Spécialisée de Lucerne (HSLU) – Cladid Wiki.
本稿について
原題:Michel Arrignon – Pédagogie de la clarinette
著者:ハインリッヒ・メッツナー(Heinrich Mätzener)
場所:マント=ラ=ジョリー(Mantes-la-Jolie)
取材日:2018年5月4日
出典:Cladid-Wiki / Haute École Spécialisée de Lucerne
Hochschule Luzern-Musik, étude : “Clarinet Didactics”, auteur : Professeur Heinrich Mätzener
(ルツェルン応用科学芸術大学 音楽学部、研究テーマ:「クラリネット教授法」、執筆者:ハインリッヒ・メッツェナー教授)
本稿は、2018年5月4日、マント=ラ=ジョリにて行われたミシェル・アリニョン氏へのインタビューに基づき、ハインリッヒ・メッツナー教授によって執筆されたものです。
シリーズ構成/目次
※各章は順次公開します。リンクは公開後に有効化されます。
1. クラリネットのフランス学派 « L’école française de clarinette » – à la recherche du canon didactique
1.1 技術的な練習は解釈と結びついている
1.2 音階練習を音楽的に行う
1.3 身体と比喩による指導
1.4 想像力の役割
1.5 すべての理論を知っても身体の使い方で伝える
1.6 模倣によって学ぶ
→ 第1章を読む(/arrignon-pedagogy-french-school/)
2. 呼吸 La respiration
2.1 管楽器を吹くというのは、空気を飲むようなものだ
2.2 息を吸うときの開きを、息を吐くときにも保つこと
→ 第2章を読む(/arrignon-pedagogy-breathing/)
3. 音色の質 La qualité sonore
3.1 流行は変わる
3.2 音可変的な音質を探求する
→ 第3章を読む(/arrignon-pedagogy-sound-quality/)
4. アンブシュア L’embouchure
4.1 二重アンブシュア(ダブルリップ)
→ 第4章を読む(/arrignon-pedagogy-embouchure/)
5. アンブシュア・ライン La ligne d’embouchure
5.1 マウスピースと身体の角度
5.2 声の形成(ヴォカリゼーション):舌は加速装置として働く
→ 第5章を読む(/arrignon-pedagogy-embouchure-line/)
6. デタシェとレガート Le détaché et le legato
6.1 均質性
6.2 レガートとデタシェ:同じアンブシュア、同じ舌の位置を保つ
6.3 反射的なデタシェ
6.4 アーティキュレーションの多様性:舌を使わない発音
6.5 スタッカートが非常に速いとき、テンポ120ではうまくいかない
→ 第6章を読む(/arrignon-pedagogy-articulation/)
※ 2026年2月中旬の公開を予定しています。
7. 指の柔軟性 La souplesse des doigts
→ 第7章を読む(/arrignon-pedagogy-finger-technique/)
8. 音程 L’intonation
8.1 音程は音楽表現の手段
→ 第8章を読む(/arrignon-pedagogy-intonation/)
9. 現代奏法 Les techniques contemporaines
9.1 スラップ・タンギング
9.2 グリッサンド
9.2.1 エディソン・デニソフのソナタ
9.2.1.1 第1楽章のグリッサンド
9.2.1.2 第2楽章のテンポ
9.2.1.3 解釈
→ 第9章を読む(/arrignon-pedagogy-contemporary/)
10. 複音(マルチフォニックス) Les multiphoniques
10.1 仕組みと生成原理
10.2 アンブシュアと気流の制御
10.2.1 教育的アプローチ
→ 第10章を読む(/arrignon-pedagogy-multiphonics/)
11. エスクラリネット(小クラリネット) La petite clarinette
→ 第11章を読む(/arrignon-pedagogy-eb-clarinet/)
12. 楽器・マウスピース・リード L’instrument, le bec et l’anche
12.1 内径、音質、そして音程
12.2 マウスピース リード
→ 第12章を読む(/arrignon-pedagogy-gear/)
13. 結論 Conclusion
→ 第13章を読む(/arrignon-pedagogy-conclusion/)
公開ポリシー(翻訳方針)
本ページは Cladid-Wiki 掲載「Michel Arrignon — Pédagogie de la clarinette」の日本語公式翻訳版です。
・原文の段落構成と語順を尊重し、内容の正確性を最優先としています。
・専門用語は、日本の音楽大学などで一般的に用いられる表記に統一しています(例:アンブシュア/デタシェなど)。
・必要に応じて、理解を補う脚注や補足を最小限に加えています。
翻訳・編集:ビュッフェ・クランポン・ジャパン編集部
翻訳公開許可:著者Heinrich Mätzener氏 および Camille Arrignon氏
© Haute École Spécialisée de Lucerne (HSLU) – Cladid Wiki.
公開スケジュール
2週間ごとの頻度で章(または統合章)を順次公開予定です。
- ハインリッヒ・メッツェナー教授(Heinrich Mätzener)は、スイスのクラリネット奏者。 ハンス・ルドルフ・シュタルダー、ギィ・ドゥプリュ、ロバート・マーセラスらに師事し、チューリッヒ(クラリネットおよびオルガン)、バーゼル、パリ、シカゴで研鑽を積む。 国内外のコンクールで成功を収め、国際的な演奏活動を行うなど、芸術的に多彩な音楽家としてのキャリアを築く。 研究者としては、ルツェルン応用科学芸術大学の准研究員として、楽器奏法と歴史的奏法を、生理学、歴史学的観点から研究するプロジェクトを2024年まで担当した。