
ブログVol.13 – シャリュモーからベーム式へ:クラリネットの歴史をたどって
国際的なクラリネット奏者として多彩な演奏活動を行い、パリ地方音楽院やローザンヌ高等音楽院で教鞭をとるフローラン・エオー氏。エオー氏がフランスで執筆中のブログの日本語版を、シリーズ化してお届けいたします。
クラリネットの歴史:シャリュモーから始まる物語

クラリネットの起源と初期の課題
クラリネットの演奏技術の発展は、楽器製作の進化と密接に結びついています。
シャリュモーからベームの可動リング・システムに至るまで、クラリネットにキーが段階的に追加されていったことで、より多くの音を、より容易に演奏できるようになりました。
キーの数が限られていた時代には、変化記号が2つ以上(♯3つや♭3つなど)の調で演奏することはほとんど不可能でした。
そのため、クラリネットは異なる調性の楽器(C管、B♭管、A管)を使い分けていました。
たとえば、イ長調(♯3)の楽譜はA管クラリネットで演奏されることで、実質的にはハ長調(変化記号なし)の譜面となるのです。

移調楽器の時代:C管・B♭管・A管クラリネットの役割
ミュラーの「全調クラリネット」構想と音色の多様性
1811年、クラリネットに十分なキーが備わり1本で全調演奏が見え始めたとき、奏者で製作者でもあったイワン・ミュラーは「三種の中でB♭管が最も優れている」と主張しました。実際、この楽器は最もバランスが取れており、音響面でも他のクラリネットを上回っていました。
ミュラーは1812年、自らの「オムニトニック(全調対応)クラリネット」を広めるために、パリ音楽院の著名な奏者たちにそれを提示しました。しかし彼らは、C管クラリネットとA管クラリネットを廃止するという考えを退けました。
実際、彼らはこう指摘したのです。
「私たちのクラリネットは、その比率の違いによって異なる音色的性格を生み出す。C管クラリネットは輝かしく生き生きとした響きをもち、B♭管クラリネットは荘重で哀愁を帯び、A管クラリネットは田園的なジャンルにふさわしい。そして、もしミュラー氏の新しいクラリネットが唯一の楽器として採用されてしまえば、作曲家はこれらの明確に異なる音色的性格を活かす資源を失うことになるのは疑いない。」
C管、B♭管、A管クラリネットの使用は、それぞれの音色の豊かさゆえに、リヒャルト・シュトラウス、グスタフ・マーラー、さらにはイーゴリ・ストラヴィンスキー(《クラリネット独奏のための3つの小品》において)といった作曲家たちによって、実際に保持され続けました。
ここで、異なるクラリネットの使用についてのエクトル・ベルリオーズのコメントを引用します。
「一般的に、奏者は作曲家が指定した楽器を吹くべきである。それぞれのクラリネットには固有の性格があるのだから、作曲家が特定の楽器を選んだのは、ある音色を得るためであり、気まぐれからではないと考えるべきだ。にもかかわらず、一部のヴィルトゥオーゾが行っているように、すべてをB♭管クラリネットで移調して演奏し続けるのは、大抵の場合、作曲家に対する不忠の行為である。」

リードの向きとアンブシュアの変遷
リード上向き奏法(歴史的な吹き方)とリード下向き奏法(現在の標準)
さまざまなクラリネットや異なるピッチが共存していた時代において、名クラリネット奏者たち(多くは製作家であり教育者でもありました)は、奏法の発展において決定的な役割を果たしました。
この時代、フランスではクラリネット奏者がリードを上唇側に当てて吹いていました(そこからマウスピース上部の支えを「マントニエール」と呼びました)。一方、ドイツではリードを下唇側に当てる奏法が一般的でした。
フリードリヒ・ベア(フランスではフレデリック・ベアと呼ばれる)はその『クラリネット奏法教程』の中で次のように記しています。
「著名なベールマン――1818年にパリで私たちが聴いたときのことですが――は、これまで知られていなかったようなピアノ表現を示しました。4小節を非常に強く吹いた後、同じフレーズを極めて弱く繰り返し、その音はまるで別室から響いてくるかのようでした。
下唇は上唇よりも強く、また可動性が高いため、疲労なくアンブシュアを保持でき、柔軟さによってより生き生きとした演奏を可能にします。この奏法は、息を妨げることなく呼吸でき、頭をまっすぐに保ちながらベルを持ち上げる必要もありません。また、舌がリードに触れることでスタッカートを奏するのにも有利です。
私は、コンセルヴァトワールの弟子たちにはリードを下唇側に当てる奏法で吹くよう指導すべきだと考えます。二週間練習すれば、彼らは旧来の方法よりもこの新しい方法を好むようになるでしょう。」
フランスで私たちが今日このように演奏しているのは、彼のおかげです。
(もっとも、ベア本人はダブルリップ奏法――すなわち上唇も歯とマウスピースの間に挟む吹き方――を用いていました。)
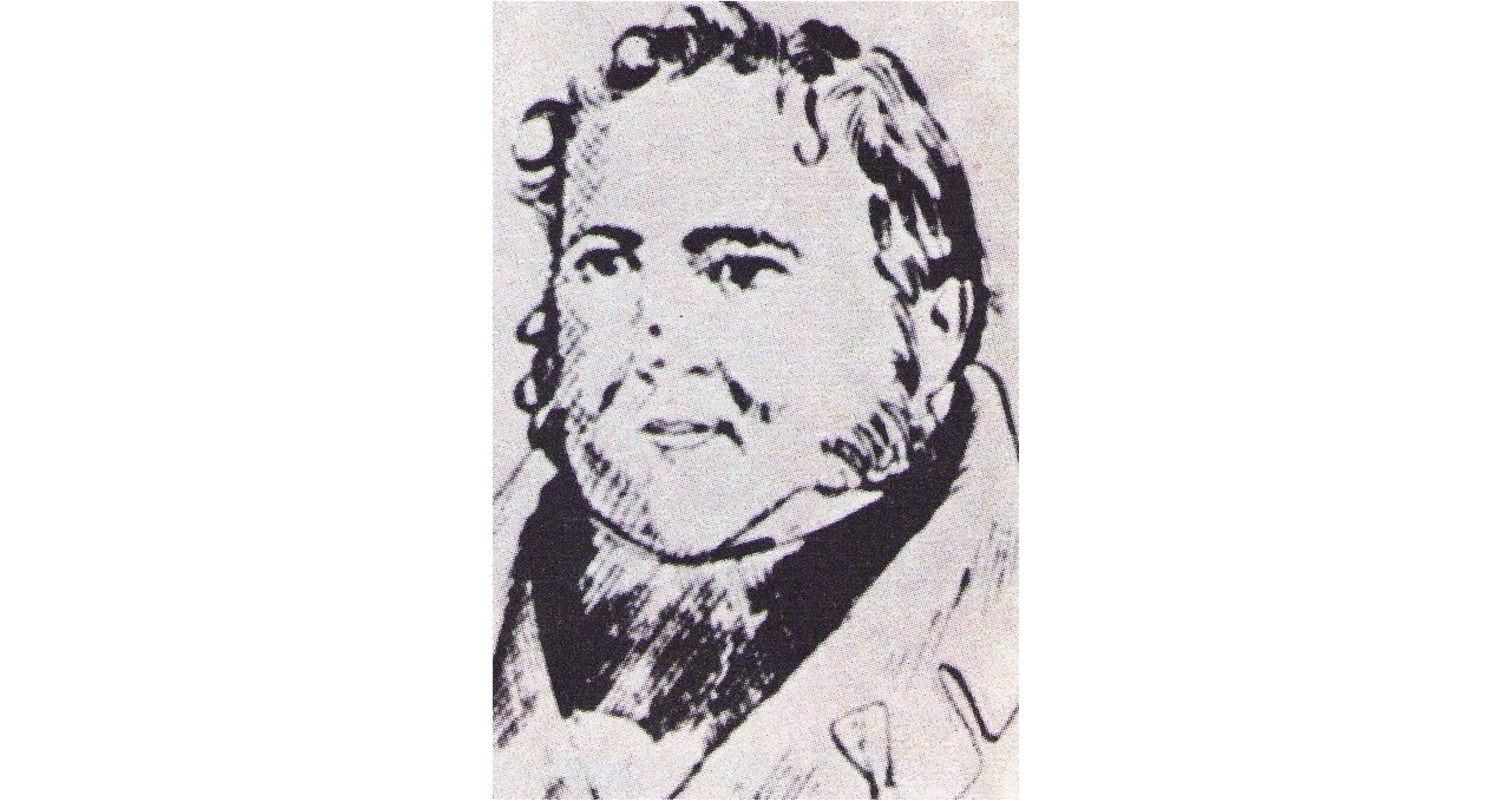
イアサント・クローゼとベーム式クラリネットの誕生
ベーム式の革新
最終的に13キーのクラリネットが採用されましたが、その後 イアサント・クローゼ が、フルート奏者で製作家でもあった テオバルト・ベーム の発明した可動リング機構をこれに適用しました。
ルイ=オーギュスト・ビュッフェとの協力で製作された試作機は、1839年のパリ博覧会に出品され、入賞を果たしました。
このクラリネットは 24の音孔を6つのリングと17のキーで制御し、シャフトに取り付けられたキーと低音域用の交差レバーを備えていました。これにより、演奏は迅速かつ正確になり、複雑な「フォークト運指(替え指)」を不要とし、低音域で指を滑らせて移動する必要も解消されました。
ベルリオーズの証言にみるクラリネットの魅力
ベルリオーズはクローゼについて次のように書いています。
「彼が楽器における最も厄介な難しさをいとも容易く克服する、その技術は彼の主たる功績ではない。彼には別の資質がある――それはアンブシュアと音色である。私の考えでは、人間の声でさえ、クラリネットの音がもつビロードのような柔らかさと憂愁を帯びた優しさにはまったく及ばない。」
このクラリネットは次第に広く受け入れられ、奏法も発展していきました。それは、クローゼの名高いメソードや数々の練習曲集の存在にも支えられてのことです。クローゼはフリードリヒ・ベアの後任として、パリ音楽院の教授に就任しました。
現代クラリネットの系譜:フランス式とドイツ式
今日、私たちが演奏しているクラリネットは、このクローゼのクラリネットに非常に近いものです。一方、主にドイツやオーストリアで用いられている「ドイツ式システム」のクラリネットは、直接的にミュラーのクラリネットを起源としています。

※ 本記事は、フローラン・エオー氏のご承諾のもと、2010年2月26日に公開されたブログ記事を株式会社 ビュッフェ・クランポン・ジャパンが翻訳したものです。翻訳には最新の注意を払っておりますが、内容の確実性、有用性その他を保証するものではありません。コンテンツ等のご利用により万一何らかの損害が発生したとしても、当社は一切責任を負いません。
